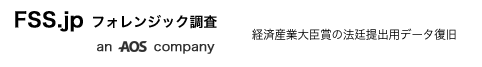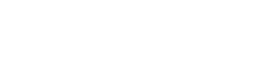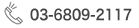6月14日 首都圏の空の玄関口、成田国際空港で「自動運転トーイングトラクター」が実運用を開始した。「自動運転トーイングトラクター」のボディに貼られたステッカーを観察すると、JALを含め、TLD、EASY MILE、SASなどの文字が誇らしげに輝いている。走行ルートは、第二ターミナルの荷捌き場(ソーティング場)からサテライト側のソーティング場までの往復1.2kmとなる。車両は、事前にルートを記憶させ、自己位置を推定しながら走行し、周囲の障害物などの検知機能を備える。コロナ禍後の旅行需要の回復に向け、成田空港第二ターミナルのサテライトエリアの稼働が再開されたことに伴う、荷捌き量の増加に備える。同社内ではコロナ禍以前の航空需要の拡大に対し、グランドハンドリング業務において、生産年齢人口の減少に伴う労働力不足が課題となっていたが、JALは先進技術を活用して航空イノベーションの推進を図り、コロナ禍後の航空需要に対しても、きちんと対応できるよう、自動運転を利用したトーイングトラクターの自動運転に向け、官民連携し導入を推進してきた。ちなみにJALグループでは、手荷物や航空貨物を運搬する「トーイングトラクター」をに日本国内に約900台保有(空港内で使用する車両としては最多)しており、社内資格を取得した社員が日々安全第一に運行を続けている。JALは、2022年5月に日本の航空会社で初めて、成田国際空港の車両通路において手荷物用の自動運転トーイングトラクターを「運用」*を始め、危険時の回避操作をする運転者が乗車する「自動運転レベル3」でのを実現させている。*2019年10月より成田国際空港の制限区域内において、自動運転トーイングトラクターの運用に向け、課題解決の取組みを開始。実証実験(JAL、成田国際空港㈱)は10月31日より開始している。*ちなみに、2019年10月31日~2020年3月31日まで行われた、実証実験に用いられた車両は、仏TDL社の「TractEasy」、自動運行管理システムはSBドライブの「Dispatcher」、実証実験のサポートはSAS(Smart Airport Systems)社が行った。「TractEasy」には、予め設定した経路を自動で走行させることが出来、走行時には、車両屋根に搭載されたGPSアンテナ、LiDAR、バンパー両脇に設置されたLiDARなどから、収集されるデータで車両の位置情報や他の車両、歩行者との距離を検知することで、精密で正確かつ安全に走行することができる。車両にはその他、走行距離計や慣性計測ユニットが搭載されているようだ。自動運転ソフトウェアとしては、仏「EasyMile」社のソフトを用いている。遠隔運行管理システム「Dispatcher」は、自動運転車両の運行管理を行うシステムであり、オペレーターは遠隔地で車両の速度や位置を把握し、管理することが出来る。加えてEV車である「TractEasy」に搭載されたバッテリー残量や走行距離など車両の走行ログの記録や分析が出来、走行経路上で課題になりやすい場所も抽出することが出来るので、より安全性の高い車両運行に向けた検証を可能としている。2019年9月20日当時のJALリリースにおいては、今後は自動運転車両の運行経路を、設定済みの経路の範囲内で任意に組み合わせる機能や、車両に運行指示を出す機能などの実装を目指すとしていた。導入までの道のりは平坦ではなく、ソフトウェアの改善や走行経路の微修正などを重ねてきたという。実証実験以降では、雨粒がLiDARのレーザー光を乱反射させないよう、雨粒が直接当たらないようカバーを設けたり、走行コース上の段差によるLiDARの走査に誤差が生じる問題を改修したり、交差点などで対向車を認識しやすくするため、LiDARの走査範囲を広げたり、加減速をスムーズにする、また安全に配慮しながら、走行スピードを段階的に引き上げる、牽引機材を追加して走行させる、などの工夫もしてきた。現場では、作業負担の軽減を図ることで、安全性の向上につなげようと試みる。具体的には、車両運転を自動化させることで、走行する車両周囲の監視に専念できるため、全然状のメリットは大きいという。二つ目のメリットとして、「自動運転トーイングトラクター」はEVであり、軽油燃料を必要としないため、CO2を排出しないことだ。同社は、今回の運用を開始した「レベル3」に止まらず、「完全自動運転」(レベル4)を目指すとしている。*国土交通省は、空港内の牽引車について2025年に「レベル4」を導入することを想定している。一方、JALの永遠のライバル、よき相方とも言えるANAの動きはどうだろうか?ANAは、羽田空港において豊田自動織機と手を携え、自動運転トーイングトラクターによる貨物搬送を念頭に置いた実証実験を2021年3月29日~4月2日に羽田空港内の制限区域において行っている。この実証実験に使用した豊田自動織機の車両(*本製品は、2021年度グッドデザイン賞においてもグッドデザイン・ベスト100を受賞している)は、周囲の状況や自車および目的地の位置を的確に認識し、安全かつ正確に走行するための技術として、2D/3D LiDARによる障害物検知と自動停止、路面パターンマッチング、GNSSによる自己位置推定、誘導機能が搭載されている。実証実験に使用されたトーイングトラクターは(3TE25)*https://www.toyota-shokki.co.jp/news/2021/10/25/004567/、豊田自動織機が2021年10月に全国40社のトヨタ&F取扱店を通じて販売された車両。2021年7月には、成田空港や羽田空港等国内21空港が、国土交通省より「重点調査空港」に選定され、空港施設や空港車両から排出されるCO2削減の取組みがスタートしているが、このようなニーズの下、3TE25は電動化され、高効率モーターやドライブユニットを搭載し、牽引力・走行速度・登坂能力などエンジン車と同等の走行性能、高容量バッテリーの採用により長時間の連続稼働を実現している。ちなみに一台あたりの価格は、7,680,000円という(メーカー希望小売価格)。*同じ型番が付されているが、実証実験で使用された車両(https://www.anahd.co.jp/group/pr/202103/20210322.html)とは、意匠が異なる点にも注目した。豊田自動織機が新たに開発した車両で、レベル3で運行されている。コースは西貨物上屋~407番スポット~西貨物上屋までの1週3kmとなった。この実験では、6連結ドーリーを牽引し走行した。両社は、これまで(2019年2月~)、九州佐賀国際空港と中部国際空港において、自動運転トーイングトラクターの実用化に向けた実証実験を重ねて来た。これらの成果をもとに、多くの航空機や、複数種の支援車両が混在する国内最大の羽田空港でも、自動運転トーイングトラクターが実用に耐え得るかについて検証を進めている。本実証実験において導入された豊田自動織機の新型車両は、取り扱い貨物量が多く走行条件の厳しい羽田空港での運用に対応するため、屋内外をシームレスに自動走行できる自己位置推定機能を有し、牽引重量の増加、坂路走行にも対応可能な走行性能を実現させたものだという。さらに豊田自動織機が開発した樹脂製のウィンドウをキャビン部分に採用、雨天や強風などの環境下においても、走行の安全性を向上させるとともに、意匠や車体軽量化にも配慮したデザインとなっている。実験に用いられた車両の制御技術は、路面パターンマッチング(車両に搭載したカメラで撮影した路面画像と事前に作成した路面画像マップデータをマッチングすることで、車両の位置・姿勢情報を取得する技術)と、GNSS(高精度衛星測位)、3D LiDAR(対象物にレーザー光を照射し、その反射光を測定することで対象物までの距離を正確に測定できるセンサー、車両の周辺状況の把握に使用)だ。両社は、羽田空港での実証実験を通じ、大規模空港における運用面での課題を抽出するとともに、2021年10月からの実運航便での試験運用への布石とするとしている。両社においても、国交省の航空イノベーションの一環として、生産年齢人口減少に伴う労働力不足等に対応するため、2025年の無人搬送(レベル4)の実現を目指し、取組を推進していくという。現在もJALとANA、各社において自動運転トーイングトラクターの「レベル4」化への取り組みが進められているが、2025年を目途とする国交省は実証実験の進捗について、どのように捉えているのだろうか。ANAによる羽田空港の実証実験から、およそ1年後、2022年3月10日に行われた「第11回空港制限区域内における自動走行の実現に向けた検討委員会」の議事概要(*1)を覗いてみると、自動運転トーイングトラクター実証実験結果・進捗の項目があり、ANAが「令和3年度 自動運転トーイングトラクター実証実験結果・進捗」に基づき、説明を行っている。この委員会において、ANAは「実験車両が自己位置推定技術として路面パターンマッチングとGNSSを併用し、その他に車載センサや3Dマップ等の組合せによって安定した走行が可能であったか?」との質問に対し、GNSSとSLAMに加え、場所により磁気マーカと路面パターンマッチングを併用し、各技術の強みと弱みを補完しながら、安定した走行が出来たと回答している。実験における「課題」に関する質問には、手荷物搬送の実験当日に当初設定したルートに含まれないスポット変更により、自動搬送の検証ができなくなる事象が生じたと回答、実際のオペレーションにおいては走行可能なエリアを拡大して臨機応変な対応が求められると回答。また、手荷物ソーティング場内は、狭隘であることに加え、従業員が怪我をしないように、(車両は)極力ベルトコンベアの際まで寄り付かなければならないが、豊田自動織機の協力を得て、ルート上を性格に走行できたとアピール。今後「臨機応変」な対応を見据えるとFMSのようなシステムとの連携が重要になると発言している。現在、スポットにおいては各スポットに設定された停止位置まで自動運転を行い、そこからハイリフトローダーへの寄り付きなどは手動で実施、一方、ソーティングエリアでは作業員が手荷物を降ろすベルトコンベアの横まで、すべて自動走行を実施したと回答している。AiRO㈱からも「令和3年度 自動運転トーイングトラクター実証実験結果・進捗」に基づき説明がなされている。「今回はデータ取得を目的として実験したが、悪天候時のデータが取得できなかった理由、また夜間データは取得できているか」との質問に、同社はあ起点工事のデータ取得については、あらかじめ定めた期間に実験を実施しているため、タイミングが合わなかった旨を説明、雨天のデータを取得出来そうな日があったが、結局雪になったため、やむなく走行を断念した経緯を説明、夜間についてはデータ取得を行っていると回答している。同社の実証実験への希望はもう少し幅広にデータが取得できるよう検討して欲しいとしている。また「運用上最大200m先の認識が必要という「認識の要件」を示しているが、どのような状況下において、それが必要であるのか、どのような場合には90mで良いのか?との質問に対して、現在の車両性能では約90m先までの車両しか認識できないが、空港内には車両の走行速度もそれほど早くない、衝突は十分回避できる認識距離ではと考えている。一方空港内の規則では、あくまでもサービスレーン上を走行している車両が優先となるため、最大200mの車両が認識が必要であり、今後運用ルールも含め、検討の余地があると回答している。この点に関しては、200mや90mといった数字が独り歩きしないように、今後可能な範囲で具体的な対象個所や、判断基準について情報提供して欲しい、と締め括られている。(*1)https://www.mlit.go.jp/koku/content/001475366.pdf
MaaS・CASE関連の最新ニュース
自動運転時代、「充電マネジメント」に商機 他
6月13日 6月4日の午後11時ころ、韓国釜山市の南海高速道路のトールゲートを通過中であった現代自動車(Hyundai)の「IONIQ 5」が緩衝具に突っ込み火災が発生した。消防隊が午後11時15分頃現場に到着し、消火作業を行ったが、同車は全焼し乗員2名は車外に脱出出来ず、死亡した。監視カメラの映像からは、車両が衝突から約3秒で炎に包まれたと聞く。同車は2021年2月に現代自動車が公開した中型のクロスオーバーEVだ。衝突後、バッテリーの温度が一気に高温(約800℃とされる)になるバッテリー熱暴走が起きたものと思われる。ちなみに800℃はどれくらいの燃焼温度か?というとたばこの先端の燃焼部分(850℃)とほぼ同じ温度域だ。家庭用のガスストーブやガスコンロなどの燃焼温度は、約1700℃と言われる。火は一旦鎮火したように見えたが、再び発火、その後完全に鎮火するまで、約7時間を要したという。日経クロステックには、2021年3月5日の「EV火災事故の原因はLGの電池か、韓国企業の争いでCATLに漁夫の利」には、現代自動車の「IONIQ 5」が同グループで展開するEV専用プラットフォーム「E-GMP」(Electric-Global Modular Platform)を初めて適用した車種であることが書かれている。韓国国土交通部は「IONIC 5」の公開翌日に、自動車安全研究院と共同で実施した、現代自動車の「Kona Electric」の火災事故に関する調査結果を発表している。当時原因とみられていた電池セルの分離膜損傷に関しては、再現実験の途中であり、今のところ実験では火災が発生していないとしている。(※今回6月4日に起きたの事故原因とは異なるので、留意して読み進めて頂きたい)この際、現代自動車は、リコール関連費用の総額を1兆ウォン(当時で約954億、2022年6月現在、約1034億円)と試算し、最終的な費用は電池のサプライヤーであった「LG Energy Solution」と分担する方針を表したが、「LG Energy Solution」はこれに「再現実験では火災を引き起こさなかった」「BMS(電池管理システム)の充電マップについて、当社が提案したロジックを現代が誤って適用したのを確認した」と反論し、電池が火災事故の原因ではないとの立場をとった。この記事から読み取れるのは、韓国の国土交通部や自動車安全研究院が、バッテリーに関する事故調査を行うことが出来る立場にあるということと、再現実験の結果、EVの核心的な部品とも言えるバッテリー部分に問題があるとされた場合、自動車メーカーも電池メーカーも、それ相応のリコール費用を覚悟しなくてはならないという事実だ。また、日経の同サイトでは、EVの火災事故が世界各国で相次ぎ、衝突に伴う炎上など原因は様々だが、共通するのが事故処理の難しさあると指摘する。今回6月4日に起きたの事故と同様、一度鎮火しても、バッテリーの発熱によって再燃してしまう点が挙げられている。これの問題については米国の全米防火協会(NFPA)や米国家運輸安全委員会(NTSB)の調査結果があるようだ。米国では、2021年4月17日にテキサス州ヒューストン北部でTeslaの「モデルS」が樹木に衝突し炎上し、乗員2名の命が失われている。同年8月14日には、ドイツのVWのEV「ID.3」が、オランダで充電後に発火している。米国GMの「Bolt EV」も充電中に電池から発火した例は複数、GMは3回にわたってリコールを発表している経緯がある。これらの事故の結果、明らかになったのは、EV車両火災の危険性の高さだ。Tesla車の事故の件で消火に使われた水の量は、10万599リットルと伝わる。鎮火まで4時間を要した。通常、内燃機関車の火災の場合、消火は数分で終わる。事故の経過の記録を見ると、事故車は消防隊の現場到着後に、一旦鎮火するも、はじめの消火開始から約25分後に一度消したはずの火が「再燃」している。この件では、消防隊は事故を起こした車両を「つり上げ」、バッテリーのある車両の底面に水をかけて、再度冷却を実施している。再発火現象は、リチウムイオン2次電池(1次電池とは一度完全に放電してしまったら捨ててしまう、使いきりの電池のこと。2次電池とは充電して繰り返し使用出来る電池のこと。)は、+極と-極のショートが起こると、大電流が流れ、結果発熱し、その熱がさらに次の発熱を誘発し「熱暴走」が起こり、遂には発火を引き起こす。現在では、バッテリーが損傷した場合、「熱暴走」に至る前に電池内からエネルギーを逃がす手立ては確立されていないため、消火後の電池が再度発火に至るケースがある。発火を回避するには電池を冷却するのが最良の方法だが、電池がシャシー(車台)に搭載される車種の場合、構造的に直接の冷却が難しくなる。韓国のバッテリーメーカーである「SKイノベーション」のWebサイトを拝見すると、「SKオン」の電気自動車バッテリーの項目には、EV用、PHEV用、HEV用それぞれのバッテリーが、性能と安全に対する信頼性を最優先におき、すべての生産・供給過程において厳しい標準が適用されていることが説明されている。韓国のバッテリーメーカーである「LG Energy Solution」では、Webサイトに「リチウムイオン電池安全ガイド」を用意し、「使用と取扱いに関する注意」から始まる実に様々な注意事項や禁止事項が並んでいる。一方ジェトロ(JETRO)では、ビジネス短信で米国連邦政府独立機関の国家運輸安全委員会(NTSB)が、2022年6月1日、自動車メーカー8社*が、NTSBの勧告に従う形で、電気自動車(EV)用高電圧リチウムイオンバッテリーの火災に対する緊急ガイドの見直しを行うことに同意したと発表した。*自動車メーカーは、ホンダ、現代、三菱自動車、ポルシェ、フォルクスワーゲン、ボルボ、大型商用車メーカーのプロテラ、バスメーカーのバンホール。同勧告は2021年1月にEVメーカー22社にも提出されており、GM、フォード、トヨタ、テスラなど12社でも受け入れの検討を進めているとする。米国のEVバッテリー火災は、2017年以降、複数回発生している。最近では、GMがEV「ボルト」の火災発生後、約11万台のリコールを発表している。この勧告は、NTSBが2020年11月に発表したEV車両事故の事例分析である「安全レポート:EVリチウムイオンバッテリーの火災における緊急対応者への安全上のリスク」に基づいて行われている。EVリチウムイオンバッテリー火災時に起こる「熱暴走」の発生時に、一旦鎮火したと見えるバッテリー内部に潜む「取り残されたエネルギー」。残存すると、上記の通り再燃焼や感電事故といった「EV特有の危険性」が指摘される。自動車メーカーでは、過去「取り残されたエネルギー」の処理方法や、緊急時の対応要員(鎮火に当たる消防士や車両の牽引者など)が、晒されるリスクに関する情報が扱われていなかった。また連邦政府においても、現行の安全基準にバッテリー搭載車の高速で被害の大きい衝突事故に関する対応を盛り込んでいないことから、NTSBは、メーカーや安全基準を所轄する機関である、NHTSA(米国運輸省道路交通安全局)に対し、ISOやモビリティの専門家を構成員(約9万人)とする米国の非営利団体、SAEインターナショナルの定める基準に基づき、緊急ガイドや査定基準を作成するよう求めていた。NTSBは全米防火協会や、車両の牽引に携わる業界団体等に、同団体が提案する具体的な安全対策の実行などを促しているとする。日本国内における状況はどうだろう。国交省によると、平成21年度における自動車メーカーから、同省に報告された自動車の不具合の事故・火災情報(事故171件、火災1,053件)のうち、バッテリー付近から出火した車両火災の情報は、98件あり、要因別では、バッテリー交換作業中:28件、後付け電装品を不適切に取り付けたと推定される火災:28件が二大要因となっているようだ。このため平成22年度に当該事象に着目し、火災発生に至るメカニズムなどの調査を行い、ユーザー等への注意事項をとりまとめたとしている。翌平成22年の事故・火災情報の件数は、1,202件(事故193件、火災1,009件)だった。現代自動車は、現在ホームページ上で「IONIC 5」と「NEXO」2車種について、緊急時対応マニュアルを掲出している。「IONIC 5」のマニュアルは22頁あり、マニュアル中には、「緊急時の対応」「ロードサイドアシスタンス」が示されている。「緊急時の対応」の項目中、車両の火災>消火活動の項目には、リチウムイオンポリマー電池には、300℃ F/148℃を超える温度にさらされると、流出、発火、火花を発生させる可能性のあるゲル電解質が含まれていること、フレア燃焼効果で急速に燃焼する可能性があること、高電圧バッテリーの火災が消火されたように見えた後でも、新たな火災または遅延火災が発生する可能性があることなどが、明示されている。対処として、赤外線カメラを使用し、消火活動を終了する前に高電圧バッテリーが完全に冷却されていることを確認すること、バッテリーが再着火するリスクがあることを常に二次対応者に通知すること、高電圧バッテリーを危険にさらした火災、水没、または衝突を起こした車両を保管する際は、周囲50フィート以内に物品のないオープンエリアに保管することなどが、記載れている。また、バッテリーが燃焼すると、フッ化水素、一酸化炭素、および二酸化炭素ガスが放出される可能性があるとし、NIOSH/MSHA承認のフルフェイス自給式呼吸器(SCBA)と完全保護具を使用する必要があることにも言及がある。「高電圧バッテリーの損傷と液漏れ」の項目には、高圧バッテリーアセンブリーは、車両のシャーシ(車台 *前述のシャシーと同義)に、しっかりと取り付けられた頑丈な金属ケースに収められており、この構造は、深刻な衝突事故などが発生した場合でも高電圧バッテリーアセンブリーの損傷を防ぐのに役立つこと、このセクションでは、緊急時対応者に、損傷した高電圧バッテリーアセンブリーまたはゲル状電解液の流出の深刻さを軽減する方法に関する情報を提供しますが、そうなる可能性はほとんどありません、と記載されている。続く項目にも、対処時の注意や装備、刺激性物質への注意等が並ぶ。日本においても急速なEV普及に際して、様々なメーカーのバッテリー搭載車により、路上で同様の事故や火災が起こる可能性は否定できない。バッテリーについては、保証内容や急速充電器の普及などの話題が先行しがちだが、安全技術が「EV特有の危険性」を完全にコントロールできる域に達するまで、管轄省庁やメーカー、自動車関係機関、メディアなどは、消費者や緊急時の対応要員に、有事の「危険」に対する意識を啓発して行く必要がある。
韓国、8月からソウル江南で「自動運転タクシー」走る 他
6月10日 昨日本稿の筆者が、MaaSはどうして実証実験で終わるのか?「LIGARE」(提供:リブ・コンサルティング)という「つい気になってしまう」タイトルを見かけた為、MaaSを社会実装する際、プレイヤーにとって、なにが実装過程の障害となり、なにを理解出来れば課題解決に繋がるのかを、PwC Japanグループが2020年10月に発表した「モビリティサービスにおける事業開発」を参考に引き続きお伝えできればと思う。本資料「モビリティサービスにおける事業開発」の、3「事業化に向けた論点とPwCのアプローチ」以降は、基本的にPwCの提案的な内容となるが、実証実験を行う面々が事業開発を「内製」あるいは「外注」判断する際、内製を選択した場合「考え、実行すべき」点とも読み替えられる。本日は「考え、実行すべき」上で必要な要素を抽出できればと試みる。産業アーキテクチャに沿った、実装・事業化に向けた論点の例では、モビリティサービスの実装・実業家にあたっては、政策・戦略、ルール、データ連携など協調領域の検討が必要としている。MaaSの実施主体の協調(言い換えれば、外部連携を必要とする)領域とは、①政策や戦略、②ルール(a.社会受容性の醸成 /b.法令・規制)、③組織(競争領域でもある)、④ビジネス(完全な競争領域)、⑤機能(完全な競争領域)、⑥データ、⑦データ連携、⑧アセット(完全な競争領域)などがあるとされ、以下のような論点を各方面の関係者と話し合い、考えていく必要がある。①政策・戦略面では、地域に必要なモビリティの効率的導入のためのビジョン・マスタープラン②a.社会受容性の醸成面では、新技術・サービスの受容性の確保、地域間のサービスに関する公平性の担保、利用する交通モード変更を促す意識改革や仕組みの検討。b.法令・規制面では、データ連携、標準化、データ保護等、データ利活用に関するガイドラインに盛り込む内容。③(競争領域でもある)組織面では、多面的な(各方面との)合意形成に向けた課題抽出、連携・協調を必要とする隣接する非モビリティサービス事業者(地域の医療・介護・福祉・宿泊・小売・飲食・自治体および観光施設など)の抽出。⑥データ、⑦データ連携面では、事業者データのデジタル化に必要なもの、データ利活用推進のためのオープンデータ化、データ・API標準化や個人情報の保護のための検討事項、システム・データ連携基盤の構築・維持のための費用分担。PwCは、事業化における複数の論点を事業化させるにあたり、キーポイントを「消費者ニーズと技術、成熟度、規制、事業性の調整」や、「異業種を巻き込んだエコシステム形成」、「仮説・事業検証・改善サイクル循環と事業精度の向上」の3つに絞っている。*同社はこれらに対するソリューション(事業化パッケージ)を提供。新規事業開発のステージの全体像(大まかな流れ)は、事業モデル抽出と絞り込みから始まり、モデル評価・リスク検討+投資判断、事業計画策定とエコシステム構築、事業プロトタイプ作成と実証実験、事業化の推進の5つのステージとなる。PwCは5つのステージについて、8つのコンポーネントを用意している。事業者は外注が適当か、内製(構築を目標とするコミュニティ内で補完できるか否か)が適当か?の判断要素と読み替えれば良いかと思う。「コンポーネント」には、事業モデル抽出・選定、計画された新規事業などが実現可能かを事前に調査・検討、事業計画策定、財務モデリング作成、エコシステム構築、実証実験実行、サービスデザイン・構築、新会社や組織構築が挙がる。PwCは、事業計画の策定、エコシステムの構築(*事業主体にとっては相当の工数が予想される部分でもある)、これまで実証実験や事業化支援で蓄積したノウハウによるサービス提供などを提供している。事業者の立場からはコンポーネント単位で利用し、新事業の導入を加速を望みたくもある。同社のフレームワークを活用した場合、事業主のビジネスモデル定義、市場定義、事業領域の定義事業方針の策定などの事業モデル(事業主がありたい姿)と、技術可用性、安全性・リスク、事業性、社会的受容性、法的課題などの要素ごとの現状を評価し、そのギャップを第三者の観点から整理を受け、これらをもとにロードマップを策定、事業モデルを実現して行く。事業主にとっては、ロードマップの策定時に、「ありたい姿」と客観的な目で見た現状の把握が必要と言える。事業モデルやビジネスモデルの策定の際には、事業に必要となるステークスホルダーの整理(定義)と、ミッシングピースとなるステークスホルダーのアレンジメント(整理・手配など)と、ステークスホルダーの統括・管理が必要とされるが、ステークスホルダーは、異業種を含むため、事業の推進主体にとっては関係の構築や調整の負荷が大きく、この部分は「助け手」の存在が大きい。新たなモビリティーサービスを展開を目指す事業主体にとっては「ミッシングピース」領域も広大だ。この領域を充足させていく為には、ステークスホルダーと事業者双方のアレンジメントを行う必要がある。例えば、実証実験を展開するロケーションの確保には、ステークスホルダーとして地域関係者や、走行道路の利用許可申請の関係者などが考えられるが、道路使用許可を得るためには、参画企業(団体)として、地方自治体、警察、私道管理事業者、交通事業者にアクセスし、個別に手続きや調整を行う必要がある。同様にインフラ確保や異業種の参画を募る場合にも、様々な折衝を要し、全体のマネジメント(ターゲット設定、体制構築、PMO)等を行う必要がある。実際の工程の中では、幾何学的に増加する調整を部分的にでも、外注できるメリットは大きい。実証実験においては、計画した事業モデル(技術可用性、安全性・リスク、事業性、社会的受容性、法的課題)に対し、要素ごとに調査手法を都度組合せ、その課題を分析し解決を図るため、仮説や事業検証、改善サイクルを複数回・継続して実施し、事業精度を向上させる必要が出てくる。様々な調査(オペレーションリサーチ、ユーザーアンケート、ステークスホルダーリサーチ、ファクトリサーチ、コストリサーチ、独自リサーチ、市場・需要性リサーチ)を行うため、時間と調査工数を要する段階と言える。2日間に亘り取り上げた「課題解決」を前提に申せば、各々の地域で「MaaS」と「自動運転」が相互連携し、生産性の高い都市を実現した時、地域では新たなモビリティサービス導入の成果としてそれまでの苦労に見合った「対価」を得ることが出来る。拙い試みでしたが読者の皆様は、MaaSを実装する際「なに」が実装過程の障害となり、「どこ」を理解出来れば課題解決に繋がるのか?に対するヒントを得られたでしょうか。終わってしまった「実証実験」こそ、継続しサイクルを回すことで地域が理想のモビリティサービスを享受する「一歩手前」であることを、お伝えできていれば幸いです。
北京で自動運転タクシー始まる 「中国のグーグル」百度やトヨタ出資企業 他
6月9日 MaaSはどうして実証実験で終わるのか?「LIGARE」(提供:リブ・コンサルティング)につい気になってしまうタイトルを見かけた。6月から、外国人観光客の団体受入れが始まったばかりだが、この記事では、ポストコロナを見据え、都市型や地方型のそれぞれで模索が続く一方、モビリティーサービス開発には数多くの失敗パターンがあり、タイトルの通り「実証実験だけで終了、サービスを開始したものの想定よりもユーザー数が増加しない」との問題が生じているという。実証実験で終わってしまう「失敗パターン」を分類すると、①有望な新規事業領域が見つからない、②採算ラインを超えるためのビジネスモデルが構築できない、③事業リーダーの不在の3点が大きな要因のようだ。①の場合は、フレームワークありきでMaaSの事業化に取組み、既存の市場で勝負する、自社の強みを活かせる事業をするとの前提にとらわれ、有望な新規事業領域を見逃す、②の場合は、モビリティサービスの多くは公共インフラであり、利用者に多額のコストを支払うとの概念が希薄であるとの、サービス特性がある。他業者とのエコシステムを通じ最終的に自社にお金が流れるスキームを構築しなければならないが、実験のフェーズにおいては、この議論が十分になされない傾向がある、③の場合、事業の推進リーダーとなるべき、事業開発経験者、事業成立まで実現させた経験がある人材が不在であり、十分な推進体制を構築できないことが多いという。PwC Japanグループは、約2年前となる2020年10月に「モビリティサービスにおける事業開発」を発表している。自動車・モビリティ産業の7大アジェンダ(実行に移されるべき事柄)として挙がるのは、日本におけるMX(Mobility Transformation)について論じた資料だ。7つのアジェンダとは、「モビリティ将来シナリオ」、CX(Customer Experience)、MX、DX(Digital Transformation)、避けられぬ事業再編、両利きの経営・財務管理、進むべき方向性の探求だ。「モビリティ将来シナリオ」には、日本のモビリティに関する課題・将来シナリオ・事業モデルの考え方などが整理されている。またレポート全体では、上記を振り返りモビリティサービス事業化に向けたユースケース・事例、モビリティサービス事業化に向けた論点・アプローチ等が紹介されている。「モビリティ将来シナリオ」には、今後社会や規制、技術動向等により「移動減少」「自由移動」の2つのシナリオが地域・年ごとに「最適なバランスで導入される」とされ、このシナリオ実現に影響を与えるのは、地域や都市ごとの特徴やニーズ、各種サービスの前提となる規制や法制度の整備状況、自動運転などの技術開発状況、基盤となるデータプラットフォームの整備状況だとされる。「移動減少シナリオ」では、生活圏内の人の移動が減少、モノ・サービスの移動や余暇移動が増加するとされている。生活圏内においてはテレワークの進行により、住宅地からオフィス街への通勤は減少し、また生活圏外となる場所への移動、例えば出張なども減少する。この影響で生活圏外側の宿泊や飲食など周辺産業が衰退する。反対に生活圏外側の生産・物流施設から生活圏内へのモノの移動は増加、生活圏内においては、住宅地から商業・生活施設(学校や病院)などへの不要不急な移動は減少し、反対に商業・生活施設から住宅地へ向かうモノ・サービスの移動は増加する。また住宅地から生活圏外である観光地への余暇移動は増加するとされる。モノ・サービスへの「時間距離」、余暇活動の充実度が、(モビリティサービス事業を行う)地域の魅力を左右するとしている。「自由移動シナリオ」では、運転・混雑から解放され、安価・便利な交通手段により特に生活圏内での移動が増加するとされる。都市においては、生活圏内である住宅地からオフィス街への移動は、運転・混雑から解放され、また、都市や地方では、安価で便利な交通による商業・生活施設への移動は増加し、生活圏外である生産・物流施設から商業・生活施設へのモノの移動などは自動運転での配送により効率化される。この動きは生活圏内の商業・生活施設から、住宅街への配送においても同じことが言える。生活圏外である観光地では自動運転のインフラ整備や公共空間が増加し、ラストワンマイル・周遊の利便性が向上する。これらは、自動運転可能エリアの価値向上、交通事故の減少、交通渋滞の緩和や減少などが起こることを意味する。興味深いのは「モビリティサービス事業化に向けたユースケース」だ(と思う)。「新たなビジネス創造の方向性」では、モビリティによる事業インパクトと、既存事業のシナリオによる変化の掛け合わせが、新たな事業や価値を生むとしている。将来モビリティシナリオ(前述した社会・規制・技術動向等により、移動減少・自由移動シナリオが地域/都市ごとに最適なバランスで導入される)と、モビリティサービスの類型(既存公共交通補完/代替型、目的地連携型、空間再構成型)の掛け合わせが、モビリティサービス事業化に向けたユースケース(新たな事業・価値)を生み出す。モビリティサービスの類型について、もう少し説明すると、①(A)既存公共交通補完/代替型、②(B1/B2)目的地連携型、③(C)空間再構成型の3つの類型があり、①(A)は地方部で自家用車中心、都市部の公共交通をデマンド交通等で代替・補完することで移動体・移動空間の効率的な利用や、移動体に関わる補助金の軽減を企図する。想定されるメインターゲット(*以下、MT)は国・自治体、既存交通事業者である。②(B1/B2)は、さらに(B1)観光地(型)と(B2)小売店・施設(型)に分かれる。(B1)観光地(型)は付加価値領域として、観光地と連携したMaaSを提供することで、ユーザーの利便性・満足度、事業者収益、自治体収益を最大化する。MTは国・自治体、既存交通事業者である。(B2)小売店・施設(型)は、付加価値領域として小売店/施設(宿泊・医療施設等)と連携したMaaSを提供することで、ユーザーの利便性・満足度、事業者収益、自治体収益を最大化する。MTは国・自治体、小売店、デベロッパー、医療機関である。③(C)は、特に公共交通普及都市(人口密度が高く、土地が限られる都市)内において、人・モノの新たな移動手段によって空間利用の利便性を向上する。MTはデベロッパー、テナントオーナーである。①(A)既存公共交通補完/代替型のビジネスモデルは、スポンサー企業を募り、地域に根差したデマンド交通を提供することで、既存公共交通の補完や代替を図る。デマンド交通の運営を担う事業者は、自治体に公共交通の補完/代替機能を提供し助成金を得、エリアスポンサーには広告機会を提供し、協賛金を得、ユーザー(デマンド交通利用者)にはデマンド交通での移動を提供し、乗車料金を得るモデルだ。この事業者はエリアスポンサーを拡大しながら、今後は全国展開も計画している。②(B1)目的地連動・観光地型のビジネスモデルは、既存交通事業者との協力の下、観光地と紐づける移動を提供し、目的地連携型MaaSを展開するものだ。MaaSの展開を図る事業者は、自治体や周辺産業(観光地、小売、飲食等)から情報(データ)提供を受け、既存公共交通事業者には目的地連携型MaaSを展開する。MaaSには既存交通事業者に参加してもらい、移動手段の1つに既存公共交通を組み込む。ユーザーには、アプリ等による移動・アクティビティの検索・予約や、目的地までの移動を提供、結果、自治体らに観光客増加をもたらす。このモデルでは既存公共交通機関・MaaS・観光地の連携によるエコシステムの確立を目指す。(B2)目的地連動・小売店・施設型のビジネスモデルは、乗車費用が無料・割引となるバウチャー(各種サービスの利用券・クーポンのこと)発行により、商業施設等の集客を図り、目的地連携型MaaSを展開するものだ。MaaSを展開する事業者は、商業施設等(イベント開催時、売上が落ちる時間帯、等)よりバウチャー発行の依頼を請け、バウチャー発行・管理ツールを提供する。これにより商業施設等から発行手数料、乗車費用などを得る。この結果、商業施設等はユーザーの集客効果を得、ユーザーにバウチャーを発行して、商品やサービスなどを購入してもらうことが出来る。MaaSを展開する事業者は、ユーザーに移動手段を提供する役割を担う。このモデルは、大規模なコンサートやスポーツイベントなどが開催される際の混雑解消も視野に入れる。③(C)は、共有キッチン設備とデリバリーシステムを組合せ、飲食店を無店舗化することで、都市空間を再構成するモデルだ。空間再構成を図る事業者(D)は、デリバリー事業者(De)をパートナーとして連携しておき、自社(D)は料理人に対して調理用具やキッチンなどを提供、料理人は同社(D)を通して、アプリ等に掲載/広告を依頼、ユーザーに訴求する。広告を見たユーザーは、(D)が提供するフードオーダーシステム等を利用し、料理人に料理を注文、料理人は出来上がった料理をデリバリー事業者(De)を通して、ユーザーに提供する。料理人が飲食ビジネスに参入するハードルが低下、都市部を中心に飲食ビジネスでクラウドキッチンを活用した事業形態への転換が加速、他産業でも店舗を持たない空間シェアを通じた事業展開を生み出している。また上記以外の全く別な展開として、空間再構成を図る事業者(E)が、小売店を「モビリティハブ化」、モビリティの価値を「合わせ技」で展開することを模索する構想もある。モビリティの価値を合わせ技で展開する事業者(E)は、配下に公共交通補完/代替を図る事業者(A)、目的地連携型事業者(B)、空間再構成を図る事業者(C)と連携しておく。空間再構成を図る事業者(C)は小売店と提携、小売店をモビリティハブ化(集客・副次収益の獲得を図る)し、公共交通保管/代替を図る事業者(A)(マルチモーダルシェアリング・レンタカー提供事業者/公共交通事業者連携など)にスペースを提供する。(A)が提供する移動サービスにより(C)の小売店は駐車場数などの制約を受けず、集客を得る。また、目的地連携型の事業者(B)は、(C)からスペースの提供を受け、インフラ((E)がサービス展開する)を運営する。*インフラとはEV等が利用する充電インフラを意味する。(B)が運営する充電インフラ利用者は、(B)に充電費用を支払いつつ、さらに受電時間中に同じスペースにある(C)の小売店に滞在し、消費活動を行うことも期待できる。(E)は収集したデータを基にユーザーの移動に関する嗜好を読み取り、事業者・自治体等へ最適な移動方法の提案を行う。(続く)
アップルカーを先取り、WWDCでベールを脱いだ次世代「CarPlay」 他
6月8日 久々の「Apple Car」の続報が、6月6日(米国時間)*に米国カリフォルニア州にあるアップル本社(アップルパーク)で開催された開発者向けイベント「WWDC」(世界開発者会議)において披露された。同イベントは、Appleが毎年、開発者、学生、メディアを対象として開催している。今回は、基調講演とともに、Platforms State of the Union、Apple Developer Centerの初披露などが行われたという。また、M2チップを搭載し再設計されたMacBook Airと、アップデートされた13インチMacBook Pro、iOS 16、iPadOS 16、macOS、Ventura、watchOS 9、開発者がApp Storeでアプリ作成することを可能にする革新的なテクノロジーなども公開された。*日本時間では6月7日~11日。この場において、iPhoneと車載機器とを連携させる「CarPlay」の次世代版についても明らかにされたようだ。「CarPlay」は、オーディオ、通信、ナビゲーション、駐車場、EV充電、フードオーダーアプリなどを車上のディスプレイ上で統合管理するAppleのフレームワークのこと。次世代版は、インフォテインメントや、クラスター(速度メーターを始めとする計器類)向けなど、車内にある複数のディスプレイにコンテンツを表示でき、従来より多くの車載機能を制御できるようになる。同社の「CarPlay」は2014年3月に発表され、「CarPlay」を採用・搭載する自動車メーカー(LANDROVER、メルセデス、ポルシェ、NISSAN、フォード、LINCOLN、Audi、JAGUAR、ACURA、VOLVO、HONDA、RENAULT、INFINITI、Polestar *対応車種は2023年以降に発表)や、「CarPlay」に対応した車載機器などが、その数を増やしている。ユーザーは自身のiPhoneで利用しているアプリを、車載ディスプレイ上でも利用できるようになる。これまでは、マップや電話、ミュージック、メッセージと言ったインフォテインメント系のアプリで利用されることが多かった。今回発表された同フレームワークは、車載機器のデータを読み込み、速度計や燃料計、エア・コンディションなどをディスプレイに、配置などをユーザーの好みにカスタマイズした形で表示出来るようだ。また、ウィジェットなども拡張されており、天気や音楽、ラジオ、エアコンディショナー、スケジュール、各国の現地時間などの情報を、ダッシュボード上においても確認できるとのことだ。これらは、自動車メーカーや車載機器のメーカーが従来の姿勢を変え、車両や車載機器のデータをiPhoneに提供する門戸を開いたことで、実現できたものと思われるという。インフォテインメントで思い出されるのは、今年3月4日に発表された本田技研工業とソニーグループのモビリティとモビリティサービスの創造に向け、戦略的な提携に向けた協議・検討の開始だ。この発表では、具体的に両社において2022年中に新たに合弁会社を設立、新会社を通じて「高付加価値の」エレクトリック・ビークルを共同開発・販売し、「モビリティ向けサービス」の提供と併せて事業化していく意向を確認し、基本合意書の締結に至っている。両社がそれぞれ強みとする、モビリティ開発力、車体製造の技術やアフターサービス運営の実績(ホンダ)と、「イメージ・センシング、通信、ネットワーク、各種エンタテインメント技術の開発・運営(ソニー)」を持ちより、利用者や環境に寄り添い進化を続ける新しい時代のモビリティサービスの実現を目指すとしている。新会社からのEV車両初期モデルの販売開始は、2025年を想定しているとしている。ソニーグループ㈱の吉田憲一郎 代表執行役会長兼CEOは、「セーフティ、エンタテインメント、アダプタビリティの三つの領域を軸にモビリティの進化に貢献していきたい」とし、本田技研工業㈱の三部敏宏 取締役 代表執行役社長は、「新会社では、世界のモビリティの革新・進化・拡張をリードしていく存在を目指し、Hondaの持つ最先端の環境、安全に関する知見や技術の提供などを通じ、両社の有する技術アセットを結集し、いかにして顧客の期待や想像を超えた価値創造を図って行くか、そのような観点で幅広く、野心的に可能性を追求していきたいと思う」としている。ソニーと言えば忘れてはならない存在がある。「VISION-S」だ。同コンセプトカーの中で、ソニーはUI/UXデザインについてこう語って来た。クルマのデジタル化が進み、常時接続が当たり前となる。圧倒的な情報量が車内を満たす時、人とクルマは、情報と体験はどのような関係性に進化していくべきか?「VISION-S」のUI/UXデザインは、そのような問いに導き出されたソニーの答えだという。ソニーは、既存車のダッシュボードに埋め込まれたインジケータ類を排除、広大なパノラミックスクリーンを配置し、走行のための基本的な情報や、空調操作、お家芸のエンタテインメント、コミュニケーション、目的地情報、センサー情報などの最適な配置を試みた。サイドミラーを含むあらゆる情報の入出力をOVAL基調の流れの中に一元的にレイアウト。最大に狙いは「ドライバーが必要情報に数ミリ秒でも早くアクセス出来る」こと。プロトタイプの作成と、エルゴノミクス観点で繰り返し精度を高め、「シンプルかつ高速」に人とクルマが対話できる、理想のUIを見出したとする。パノラミックスクリーンには、ドライバーのための「クラスタディスプレイ」と中央と助手席にも「個別のモニタ」を用意した。二つの画面の意味は「連携」だ。例えば、助手席に座りながら行きたいレストランを表示、中央にはナビが表示されているとする。パッセンジャーが選んだレストランを中央のディスプレイのナビと入れ替えれば、二人で探して辿りついたレストランで、ランチを楽しむことも出来る。ドライバーとパッセンジャーの水平連携をフレキシブルにするのは「L-Swipe」と呼ばれるジェスチャー操作だ。ソニーが図る「次世代の」インタラクションが垣間見える。これらのUI/UXは、公道を走行することにより、現行の法規やISO基準をレビューし、その上で将来のデジタルコクピットはどうあるべきか、クラスタディスプレイの視認性、ステアリングの操作性、視界の中のあらゆるコントラストまでもが「設計」されたものだ。その技術の一旦は、「サイドミラー」にも反映されている。カメラとディスプレイによるデジタルミラーは、Aピラーの位置、クラスターディスプレイとの関係性も考慮され配置された。ドライバーの視線移動、ダッシュボードの上やハンドル周辺などあらゆる可能性を想定、最適化した結果だ。また「サイドミラー」は、車外(周囲のクルマ)を検出するレーダーやセンサーと連動、背後からの高速な接近や死角となる場所への侵入などの危険をドライバーにアラート(ドライバーが危険を察知しやすい様、ARで対象車両を表示)で知らせる。人間の不注意や夜間・荒天時の安全性を向上させる。ソニーは、またモバイルデバイス(スマートフォン)をクルマの一部と考え(反対の思想は多いが)、二つをアカウントでシームレスに結んだ。これにより、乗車前には遠隔から車内のエアコンディショナーを操作し、鍵の開閉、自動駐車などを実現、乗車後にはドライブレコーダーの映像を利用し、スマートフォンやリビングのTVでエンタテインメント・コンテンツとして再現させる。クルマによる移動時間の前後も、UXの一部と解釈した結果だ。UIの一端としては、OTAによるソフトウェアの更新を、継続的なモデルチェンジ(進化)と捉えた点も面白い。同社はソフトウェアの更新により、オーナーの快適性に寄与するばかりでなく、乗り換えサイクルを伸ばすことが出来、サスティナビリティに貢献できるとしている。この根底には、時々の人や社会のニーズによりUI/UXの最適解が変わるという思想がある。iPhoneと車載機器とを連携させるアップルの「CarPlay」が、エンタテインメントの域を出て、クルマのクラスター類に着目、これを可視化したのは大きな進化と言える。同じように、これまでエンタテインメントを追求してきたソニーが、インフォテインメント領域に踏み出すことを前提にした設計思想も優れたものだ。視点を変えれば、ホンダはいまインフォテインメント領域において存在感を示す「選択肢」を手にしている。さらに言えば、ホンダと協業するGM・クルーズが「価値ある選択肢」を手にしたとも解釈できる。自律運転は、いまだ発展中であり、同時に完全とは言えない技術(消費者の意識としても)段階だ。完成車メーカーが「インフォテインメント」に消費者の耳目を集めるということは、彼らにとってサービス及びオーナーカー双方における「安全・安心」のプライオリティが、依然として「エンタテインメント」より高い位置にあるという事実を示しているのかも知れない。今後もアップルとソニーグループのインフォテインメント領域での競演が、すべてのモビリティユーザーの安全確保に貢献する技術として発展していくことを願って止まない。
自動運転と韓国(2022年最新版)他
6月7日 JXホールディングスと東燃ゼネラル石油が統合され、いまや国内の石油元売り最大手と言われるENEOS。グループは新日本石油(1888年~)、ジャパンエナジー(1905年~)、東燃ゼネラルグループ(1893年~)からなる。グループの連結売上高(*2020年度実績)は7兆6,580億円、連結営業利益は2,542億円となる。連結従業員数(*2021年度3月末時点)は、40,753人、時価総額(*2021年度3月末時点)は1兆6,203億円となる。事業としてはエネルギー事業と非鉄金属の二分野となり、前者は原油・天然ガス、輸送、精製・精算、物流、販売、最終製品となり、後者は非鉄金属資源採掘、輸送、銅精錬、電材加工、最終製品となる。エネルギー事業はENEOSが、石油・天然ガス開発事業はJX石油開発が、金属事業はJX金属がそれぞれ担う。国内におけるガソリン販売シェアは第1位、約50%を占める(2020年度実績)。発電能力は164万kw(2021年12月末現在)。昨日6月6日、ENEOS㈱は日本電気㈱(以下、NEC)から承継した電気自動車充電サービス事業の運営開始について発表した。これまでNECが運営してきた電気自動車充電設備を用いたEV充電サービスについて事業譲渡契約を締結し、EV充電器約4,600基の運営を開始するとした。周知の通り、日本政府は2050年カーボンニュートラル実現に向け、EVを含めた電動車の普及を促進するため、2035年までに新車販売における電動車比率を100%とする方針で、電動車の普及を下支えするインフラ面では、2030年までにEV急速充電器30,000基、普通充電器120,000基の設置を目標に掲げている。ENEOSも「2040年グループ長期ビジョン」の実現に向け、次世代型エネルギー供給・地域サービス事業の育成・強化を図るとしている。同社は電動車普及促進に向けた環境変化を商機とし、EV充電器、150,000基のうち 6,100基(約4.06%)の運営・管理及びシステム運用を行うNECとの間で、EVネットワークの拡充および関連した新たなサービスの創出に関しての協業検討を進めて来た。今回、ENEOSがNECと譲渡契約を結んだのは、NECの持つEV充電器うち約75.4%ということになる。今後は、EV充電器の運営・管理業務をENEOSが担い、運用管理システムは、引き続きNECが提供することで合意している。ENEOSは、引き続きNECが展開する全EV充電器の運営承継および新たなサービスの創出に向け、協議を行いつつ、経路充電によるEV充電ネットワークの拡充を推進して行くとしている。ENEOSは、経路充電事業について、サービスステーション及び他社との協業によるEV急速充電、普通充電ネットワーク拡大を検討するとしており、具体的な「EV急速充電器」(*1)設置数計画については、2025年度時点で1,000基以上、2030年度時点で数千基~10,000基としており、普通充電器(*2)の設置数計画については、検討中としている。(*1)急速充電器:高速道路のSAや公共施設など外出先で行う短時間での充電を指す(10kW以上)。(*2)普通充電器:主に自宅やレジャー施設などで行う長時間駐車しての充電に用いられる(10kW未満)。これに対しNECは、昨年2021年5月20日に「サービスステーションを中心とした電動車両の充電ネットワーク拡充に向けた協業検討開始」をニュースルームに掲載しているが、電動車両(EV、PHV)の充電事業において協業検討を開始することで合意し、「基本合意書」を締結したと発表しているだけで、素っ気なさも感じる。*NECの発表時点では両社の共同発表だったが、今回のリリースはENEOS一社から発表されている。NECのリリースの中で、ENEOSは「2040年長期ビジョン」において、現在、地球温暖化問題の深刻化を受け脱炭素が世界的な潮流となる中で、日本国内においても脱炭素化に繋がる電動車両の普及が想定されるため、ENEOSのサービスステーション(SS)網を活用し、電動車両への充電サービスの創出を目指すとしている。また同時に地域のモビリティ関連や生活関連サービスを提供する拠点として、SSの生活プラットフォーム化を掲げている。NEC自身は「NEC 2030VISION」において「地球と共生して未来を守る」を掲げ、NECが持つAIやIoT技術を駆使し、企業などが保有するエネルギー設備の効率的で最適な運用を図ることなどを通じて脱炭素社会の実現に貢献するとしている。このリリース中では、ENEOSが全国に展開するサービスステーションは13,000ヶ所とされており、SS網および電力事業を持つENEOSの強みと、充電(実績・状態)管理や設置工事・トラブル対応など、電動車両充電器運用にかかわるシステム全般のノウハウを持つNECの強みを活かし、両社は電動車両充電ネットワークを通じた新たなサービスの創出、電動車両充電ネットワークの拡充の事業領域で協業するとしていた。1994年度末に国内に6万421店あったガソリンスタンド店舗数は、2020年度末で2万9005店と、20数年で急激にその数を減らしている。原因にはガソリン自体の需要縮小で経営が立ち行かなくなる店舗が増加していることなどがある。店舗を集約したり、自治体が整備して企業に運営を任せる「公設民営型」店舗を設けた場合などには、政府が補助金を出すなどしている。経済産業省は2022年度の概算要求で14億円を要求する。政府が補助金を出すケースとしては、利用が減った店舗を集約したり、幹線道路沿いをはじめ利用が見込める場所へ新設する場合も想定している。コンビニエンスストア、飲食店の併設など、経営の多角化も促す。店舗対策だけでなく、後継者や人手不足に対応するため、利用客の監視業務を省人化出来る技術の開発を支援するなどしている。今後も、脱炭素の流れを受け、2035年までに国内で販売される新車は、EVやハイブリッド車と言った電動車になっていく。このような流れを受け、ガソリンの需要は減速を続け、同時にガソリンスタンドの廃業も進むことが懸念されてきた。電動車への切り替えまでの過渡期には、ガソリン車は交通手段が限られる地方などで、引き続き利用・維持されていくため、現在のガソリンスタンド数の減少は、地方で深刻な問題となっている。ガソリンスタンドは、自動車への給油機能だけでなく、寒冷地での灯油配送などの機能も担って来たため、この問題への対応が急がれる。ENEOSがEV充電器の運営・管理業務と同時に、SSで進めようとしているモビリティ関連・生活関連のサービス提供が、充電事業の進展により、家庭で行われる充電とは一線を画した新サービスに育ち、再活性化することを期待したい。一方でENEOSは、燃料電池自動車(FCV)の普及も見据え、水素事業も手掛けている。政府は2014年4月に「エネルギー基本計画」を閣議決定し、同年6月に経済産業省が「水素・燃料電池戦略ロードマップ」を策定しており(2016年3月に改訂)、その後2017年12月には2050年までの普及ビジョンと2030年までの具体的な行動計画を示した「水素基本戦略」などが関係閣僚会議により策定されている。経産省の「水素・燃料電池戦略ロードマップ」によると、燃料電池自動車(FCV)は2020年までに4万台程度、2025年までに20万台程度、2030年までに80万台程度の普及台数目標があり、2025年頃に、より多くのユーザーに訴求するため、ボリュームゾーン向けの燃料電池自動車の投入を目指すとしている。ロードマップ中にある「水素ステーション」の項目には、整備目標や自立化目標が明示されている。2020年度までに160ヶ所程度、2025年度までに320ヶ所程度となっている。2030年度時点のFCV普及台数目標に対し、標準的な水素供給能力を持つ水素ステーション換算によると、1000基程度が必要とされる。また2020年代後半までに水素ステーション事業の自立化を目指すとしている。これまでENEOSの成長の一翼を担って来たのは、全国津々浦々にあるサービスステーション(SS)だ。ガソリンの需要減少にあえぐSSに対し、EV急速充電設備の投入は急がれるべきだが、充電スポットという意味では、他にもカーディーラーやコンビニ、多様な商業施設、道の駅、サービスエリアやパーキングエリア、集合住宅、個人の住宅など競合が多い。それゆえ、SS救済においてEVの急速充電設備の投入だけでは、十分な救済策とは言えない。反対に太陽光パネルや水素製造装置の新設を要する既存SSの水素ステーション化は、競合を退けることは出来る可能性が高いものの、当面ガソリン車程の消費需要を取り込むことは出来ない。ENEOSの視線は、次世代型エネルギー供給・地域サービスに注がれている。大きな視点としては洋上や陸上風力、太陽光発電、CO2フリー水素の輸送・発電、太陽光+蓄電池、モビリティサービス、エネルギーサービス(*充電含むSS)、ライフサポートなどだ。これらをVPP(バーチャル・パワー・プラント)で結び、インフラネットワークを構築、データベースやデータ分析PF構築につなぐ。ENEOSが構築するプラットフォームは、「モビリティサービス」として、カーメンテ、カーシェア・リース、お届け車両、経路充電、EV関連サービス、EVライドシェアが、「ライフサポート」として、コンビニやカフェ、ランドリー、宅配BOX、ヘルスケア、洗濯宅配・代行、訪問型生活サービスが、「エネルギーサービス」として燃料油、ENEOSでんき・都市ガス・水素、自家消費支援、VPP事業、コミュニティ向け事業などが想定されており、あらゆるデータを連携・データベース化し、アプリを通じて顧客が必要とする利便性の高いサービスの構築に力が注がれている。これらのモビリティサービス、ライフサポートサービスを包含することで、これまで培ってきたENEOSのブランド力、SSの顧客接点や、特約店の地域密着性などの強みを活かすことが出来るとしている(参考:「JXTGグループ 第2次中期経営計画 2020~2022年度」)。ENEOSは、2021年8月に「国内初となる水素ステーション内で製造したCO2フリー水素の商用販売開始について」として、横浜旭水素ステーションにて水電解水素の製造販売を始め、それまで、同社の水素製造出荷センターで製造した水素の販売を行って来たが、今後はそのような水素に加えて、当該水素ステーションに設置した太陽光パネルで発電した電力と、ENEOSグループから調達した再エネ電力を使用して、横浜旭水素ステーションの敷地内で水を電気分解し、製造したCO2フリー水素を販売するとしている。SSの水素ステーション化を具現化した試みだ。このステーションに、「モビリティサービス」「ライフサポート(サービス)」「エネルギーサービス」とのコンテンツを付加し、全国に展開してゆくことは(これまで燃料共有に携わって来た人材の再教育や育成などの難しさはあるものの)、SS救済策として現実味のある取組みであると評価出来よう。カーボンニュートラルの最前線に立つエネルギー産業。地球温暖化の回避(脱炭素)、再エネ蓄電池のコストダウン加速、省資源化などマクロな視点から、インターネットやブロックチェーン技術の利用や取り込み、AIやIoT・ロボットの活用による生産性の向上、EVシフト・自動運転などデジタル革命への対応、アジア各国の経済成長、人生100年時代、都市過密化、まちづくりニーズ、利便性追求(コト消費)、所有からシェアリング、SS持続に至るミクロな視点まで、顧客やパートナーのライフスタイルの変化にも、非常に幅広い対応が求められている。今この時も、創業から100年を数え様々な時代の変化に対応し生き抜いて来た企業の真価は、世界から問われ続けている。
ENEOS EV充電事業を強化へ NECから充電ネットワーク運営権取得 他
6月6日 電池開発においては、安全・長寿命・高品質・良品廉価・高性能という5つの要素をいかに高次元でバランスさせるかを重視する。このために「電池と車両の一体開発」が欠かせないとする。言わんとするのは、電池の使われ方は、車両がどう使われるか次第ということだ。例えばタクシーや通勤といった「使用条件」や「使用地域」などにより、「充電頻度」や「電池の温度」など電池の「使用環境」が異なってくる。これらを車両走行模擬試験により再現し、使用環境データを入手、使用条件に応じた電池の評価や設計にフィードバックする。前述の5つの要素をバランスさせるため、走行条件や走行環境の実走行データを蓄積し、電池に置き換えたらどのような条件になるか、電池の内部に何が起きているのかなどを把握し、検証を繰り返す。この蓄積が電池と車両の一体開発に繋がり、トヨタ車の優位性を生み出すとしている。トヨタの電池開発の取組み(*リチウムイオン電池の例)は、①安全性追求、②長寿命化、③高品質の3点に着目して行われる。①では、クルマがスポーティーな走りなど電池に大きな負荷がかかる場合には、電池セル一つ一つに局所的な異常発熱の兆候が見られることが分かっている。この現象については電池の中で起こる現象を解析、膨大なモデル実験を行い、走り方が電池内部に与える影響とそのメカニズムを解明する。この結果をもとに、電圧・電流・温度について個々の電池セル、セルの集合体であるブロック、そして電池パック全体を「多重監視」し、局所異常発熱の兆候を検知している。そして減少を未然の防止する電池制御を行っている。②については、HEV用の電池開発で培った技術をPHEVに活かしている。「C-HR」のBEV用電池は、それまでのPHEV用電池より「10年後の容量維持率」を大幅に向上させている。5月12日に市場投入された「bZ4X」搭載の電池では、同容量維持率90%を目指して開発が行われた。③については電池の製造工程において、内部に金属の異物が入り、正極と負極が直接つながると電池の故障に至る可能性がある。これについては、工程内で入り込んでしまう遺物の形状・材質・大きさと耐久性への影響を確認し、電池へ影響を与える関係性を明確にした上で、これら異物が発生しない様、また電池内に入らない様対策をとっている。同社はこれら「電池と車両の一体開発」により、電池コスト半減を図り、リーズナブルな車両価格設定に繋いでいる。電池そのもののコストを材料や構造の開発により30%低減。車両全体としては電費(距離あたりの消費電力の指標)を「bZ4X」以降、30%改善することを目指す。2020年代後半には「bZ4X」と比較した、台当たりの電池コストの50%低減を目指すとしている。また、次世代リチウムイオン電池(長寿命化、高エネルギー密度化、小型化、低コスト化が念頭に置かれる)の開発については、液系電池では「材料の進化、電池構造の革新」に挑み「全固体電池」の実用化も目指している。特に「全固体電池」では、高出力、長い航続距離、充電時間短縮などを狙った開発を進んでおり、2020年6月には「全固体電池」搭載車両の走行試験を実施、走行データを得た。8月にはナンバーを取得の上で、更に走行試験を行っている。一連の開発ではイオンが電池の中を高速で動くため、高出力化が期待できることが分かった。一方では、固体電解質の間に隙間が出来て劣化し、寿命を短くするなどの課題も見つかり、固体電解質の材料開発が進められている。同社は「全固体電池」は、ノウハウの蓄積が進み、高出力化が求められるHEVから導入を進めることを決めたとしている。トヨタは、電動車両が急拡大する状況においてグローバルに様々な顧客のニーズに対応できるよう、また必要なタイミングで必要な量を供給できるよう供給体制の構築を急ぐ。「安心してお使いいただける」電池のため、一定量の「グループ内生産」で技術を確立、「コンセプトを理解・実現できるパートナー」と連携・協調していくとしており、既に新たなパートナーとの協議も進めている。トヨタの言う「コンセプト」とは、生産のアプローチでは「原単位で立ち上げる」「必要な時に、必要なものを、必要な分だけつくる」というリスクを抑え込んだ伸ばし方をいう。工場にあて嵌めて言えば、BEV用の大規模なラインを一挙には作らない、小さい電池で、開発になれたHEVから市場投入するという方針が見えてくる。「HEVから始める」ことで、市場投入の加速、製造技術の向上を目指すと同時に、製造コストを下げ、安定期を迎える頃、次世代(電池)が出てくるライフサイクル対応のために「小さな原単位で立ち上げる」という戦略を取るとする。トヨタは1997年のプリウス発売以来、PHEV、FCEV、BEVの投入を続け、2021年7月までHEVの累計販売台数は1,810万台に達する。同社の試算(換算)では、これまで製造したHEV用電池は、約26万台のBEVに搭載する電池量と同等で、これまでHEVの普及により(=少ない電池量で)約550万台分のCO2排出量の削減効果があったとする。これらの電池技術は、市場でどのように生かされるのか。2020年12月に市場投入された「MIRAI」(*燃料電池自動車/FCEV)のフルモデルチェンジ車は、顧客に「このクルマはいい、本当に欲しい」と思ってもらえる未来のプレミアムカーを目標に開発されている。同社は水素社会実現を目指すFCのシステムサプライヤーとして、同車のFCスタックやエア供給・水素供給・冷却・電力制御などのFCシステム関連部品をコンパクトにパッケージ化したモジュールを開発、様々な事業者向けに提供を始めている。北米では、同社の搭載している第二世代FCシステムを採用したFC大型商用トラック(荷重量:約36トン、航続距離:480km以上)の新型プロトタイプを発表している。同トラックでは、貨物輸送オペレーションでの実証を進めていくとしている。またトヨタは、カーボンニュートラル(CN)という電池開発の上位階層においては、水素から作る「e-Fuel」やバイオ燃料などの「カーボンニュートラル燃料」と「高効率エンジン+モーター」の複合技術を組合せ、大幅なCO2削減を行うという、新たな視点での取組みにも着手している。この方法は既存のインフラを活用できるだけでなく、すでに利用されているすべてのクルマでCO2の削減を図ることが出来るというもの。「e-Fuel」は一定量をガソリンに混ぜると、ガソリン車のCO2排出量がHEV並みに、HEVではPHEV並みに、PHEVではより一層BEVに近づけることが出来るとしている。2050年CNを実現するまでの、過渡期に並走し続ける「残存ガソリン車」対策にも、視線を注ぐ。豊田社長の表現した「全方位戦略」の一端が、ここにも存在する。「カーボンニュートラル実現に向けた取組み:水素エンジン」では、同社が2021年4月から水素エンジンの技術開発に取組んでいることが発表された。燃料電池自動車(FCEV)が水素と空気中の酸素を化学反応させて、電気を起こしモータを駆動させるのに対し、水素エンジン車は既存のガソリンエンジンに一部変更を加え、水素を燃料として直接燃焼させることで動力を得る。燃料は「ガソリンとミックスしない」100%純水素だ。水素エンジンはCNにも貢献できる大きな可能性を秘めた技術であり、日本の自動車産業においてエンジンに関わる雇用を守る「選択肢」の一つとなる。2020年末に豊田社長自ら試作車に乗り、「スーパー耐久シリーズ2021」*に参加、この技術をモータースポーツの現場で鍛えて行くことを決めたという。理由は、モータースポーツにおける現場の開発の時間軸が、量産車に比べ圧倒的に短時間であるからだ。カーボンニュートラル実現には、エネルギーを「つくる」「はこぶ」「つかう」の選択肢を拡張していく必要がある。トヨタの動きを起点に、賛同を示し、連携・協働を決めた企業も増えていく。*スーパー耐久シリーズ2021:日本国内で行われる市販の四輪車を改造したマシンで勝敗が争われるツーリングカーレース。同レースのクラスの多くは市販の量産自動車に対し、小規模な改造を施した車両が使われる。個人規模のプライベーターチームの参戦が多いが、自動車メーカー系の参戦も。この場合は人材育成や車両開発が目的であることが多い。「偉大なる草レース」「S耐」とも呼ばれ、親しまれている。同年5月に富士で行われた第3戦の24時間レースは「つかう」に着目し、水素エンジン車がレース走行することを「スーパー耐久機構」(*シリーズの統括組織)が後押し、基幹部品の開発にはデンソー、水素供給には岩谷産業、大陽日酸、福島の「FH2R」などが参画している。ちなみにレースに参加した水素エンジン車は24時間完走を果たしている。同年8月に大分で行われた第4戦では「つくる」の選択肢を拡大、大分県九重町にある大林組の地熱発電、福岡県宮若市にあるトヨタ自動車九州の宮田工場の太陽光発電により精製された水素が使用されている。また翌9月に開催された第5戦では「はこぶ」をテーマに、川崎重工業、岩谷産業、電源開発が連携し、取り組むオーストラリア産褐炭由来の水素を使用している。水素の国内の運搬は、Commercial Japan Partnership Technorogiesが取組む、FC小型トラックとトヨタ輸送のバイオ燃料トラックが担当し、運搬の領域にも選択肢を拡げた。11月の第6戦では、内燃機関を利用した燃料の選択肢を広げる仲間づくりが進んだ。川崎重工業、SUBARU、マツダ、ヤマハ発動機の各社とともに、①CN燃料を活用したレースへの参戦(マツダ:次世代バイオディーゼル燃料を使用、SUBARU・トヨタ:バイオマス由来の合成燃料を使用、2022年スーパー耐久シリーズに参戦)、②二輪車などで水素エンジン活用の検討(川崎重工業、ヤマハ発動機:共同研究の検討を開始)を公表、本共同研究では本田技研工業、スズキを加えた4社でCN実現への可能性を探っていく。日本国内の自動車や自動二輪メーカーにおいて「カーボンニュートラル」に向けた様々なイノベーションの機運が芽吹いている。これらを自動運転技術やカーボンニュートラルなど、多岐に渡るグローバルの潮流において結実させるため、旧来の様々な枠を越えていく「モノづくり」が必要とされる段階だ。
次にEV購入の可能性「非常に高い」増加も課題は販売価格、米民間調査 他
6月3日 2021年の暮れに日産は長期ビジョン「Nissan Ambition 2030」を発表している。主な項目は、1.今後5年間で約2兆円を投資し、電動化を加速するとともに、2.2030年度までに(発表後10年間で)電気自動車15車種を含む23車種のわくわくする新型自動車の投入、グローバルの電動車のモデルミックスを50%以上へ拡大、3.全固体電池を2028年に市場投入するとしている。この長期ビジョンは2050年度までに製品のライフサイクル全体で、カーボンニュートラルを実現するという日産の目標を支えるものだ。内田誠社長は、「Nissan Ambition 2030」では電動化の時代に向け、先進技術でカーボンフットプリントを抑制、新たなビジネスチャンスを追求して行くとしている。カーボンニュートラルに向けた電動化の目標達成に向け、ラインアップには「EV」と「e-POWER」*搭載車が設けられ、(2030年度までの中間地点となる)2026年度までに2系列を併せ、20車種が導入される予定であり、国内においては電動車の販売比率を55%以上にするとの目標を置いている。2022年6月現在「EV(電気自動車)」のラインナップは「アリア(539万円~)」「リーフ(約371万円~)」と市場に投入されたばかりの「サクラ(約240万円~)」の3車種だ。「e-POWER(電動車)」は、「ノート オーラ(約261万円~)」「ノート(約202万円~)」「キックス(約276万円~)」「セレナ(約323万円~)」の4車種となる。*「e-POWER」は、高出力モーターとエンジンの双方を動力とする。電動化の核となるリチウムイオン電池はコバルトフリー化され、2028年度までに1kWhあたりのコストを現在(2021年)と比較し、65%削減するとしている。また、2028年度までには自社開発の全固体電池(ASSB)を搭載したEVを市場に投入することを目指し、2024年度までに同社の横浜工場内にパイロット生産ラインが導入される予定だ。ASSBのコストは、2028年度当初は、1kWhあたり75ドルとするが、その後EV車とガソリン車のコストを同等レベルにするため、65ドルまで低減して行くことを目指すとしている。グローバルな電池の供給体制は、パートナーと協力して、2026年度までにグローバルな電池生産能力を52GWh、2030年度までに130GWhへと引き上げる予定だとした。グローバルでは、EVの生産と調達の現地化を進める。英国で発表した「EV36Zero」*を、日本、中国、米国を含む主要地域で拡大、カーボンニュートラルを目指す。*日産の「EV36Zero」は、2021年7月に日産の英国法人が、欧州におけるカーボンニュートラルの実現に向けた取組みとして、英国のサンダーランド工場を中心にカーボンニュートラルへの取り組みを加速させ、ゼロ・エミッション実現に向けて新たに360度のソリューションを確立したもの。同社とエンビジョンAESC(*車載用高性能リチウムイオンバッテリー設計製造会社)、サンダーランド市議会により10億ポンド(約1659億円)が投資され、「新世代のクロスオーバーEV」「次世代のEV用バッテリーの生産」「再生可能エネルギー」という相互に関連した取組みにより実現される。一方のトヨタは電気自動車(EV)や水素燃料電池自動車についてどのように考えているのだろうか?トヨタの発表した「統合報告書 2021」を読んでみた。「カーボンニュートラル実現に向けた取組み:バッテリーEV戦略」の項目に2021年12月14日に開かれた電気自動車(BEV)戦略についての説明会の内容に触れられている。トヨタは2030年のBEV年間販売台数については、200万台から300万台に上方修正している。レクサスが同年までに欧州、北米、中国でBEV100%を、グローバルで100万台の販売を目指し、2035年にはグローバルでBEV100%を目指すとしている。トヨタにとってBEVは、カーボンニュートラル戦略の「有力な選択肢」と表現されている。トヨタはすべての電動車は使うエネルギーに拠り、二つに大別されるという。一つはCO2排出を減らす「カーボンリデュースビークル」、もう一つはクリーンなエネルギーを使いCO2排出をゼロにする「カーボンニュートラルビークル」だ。トヨタのBEVの旗艦は「bZ」シリーズだ。トヨタは同車でCO2等のネガティブインパクトをゼロにしつつ、将来を見据え、BEV専用プラットフォームを開発している(bZ4XはSUBARUと共同開発)。同車では1kmあたり必要なエネルギー量は125kWhを目指した。同社は今後「カーボンニュートラルビークル」の選択肢を広げ、2030年までに30車種のBEVを展開、BEVのグローバル販売台数は、同年で年間350万台を目指すとしている。トヨタが水素燃料電池車一途ではなく、BEVを選択肢に残す理由を、豊田社長は「経営的な話で言うなら、選択と集中をした方が効率的かもしれません。しかし、私は未来を予測することよりも、変化にすぐ対応出来ることが大切だと考えております」と語る。また豊田社長は「BEVシフトか?全方位戦略か?」との問いには、各国のエネルギー事情の違いを上げ、「お客様が度のメニューを選ぶかは、われわれトヨタにはどうにもできないことです(中略)市場やお客様の動向が分かったら、素早く追従して行く。これこそが会社の競争力を上げることにつながり、生き残る一番の方法である」と答えている。また「統合報告書 2021」中の「カーボンニュートラル実現に向けた取り組み:電池の開発・供給」においては、同社の電動車の未来を「電池と車両の一体開発」で切り拓くとの方針の下、さまざまな取り組みについて触れられている。トヨタは電動車のフルラインアップを進める中、電池についても同様の方針を取る。電動車のタイプに合わせ、ハイブリッド車(HEV)は「出力型(瞬発力重視)」、プラグインハイブリッド車(PHEV)および電気自動車(BEV)については「容量型(持久力重視)」の開発を進める。HEV用電池にはニッケル水素電池とリチウムイオン電池の特長を生かした電池を継続的に進化させて来た。2021年7月に発売された「アクア」(*フルモデルチェンジ車)に搭載されたニッケル水素電池は新たに「バイポーラ構造」を採り入れ、旧型アクアに搭載された電池と比較し、同じ体積で出力密度を約2倍まで向上させ、パワフルな加速感を得られるものとした。2020年代後半には更に進化させた新型リチウムイオン電池の投入を図るとしている。(続く)
トヨタとイオン東北、水素燃料の移動販売車 福島で投入 他
6月2日 トヨタと水素の関係が活発化してきた。6月1日 福島県の双葉郡双葉町(伊澤 史朗町長)と同郡浪江町(吉田 数博町長)の2町で、トヨタ自動車㈱とイオン東北㈱のFCV(燃料電池車)による食料品や日用品の移動販売が始まる。4者は、この5月31日に「特定復興再生拠点区域等における水素燃料電池自動車を活用した移動販売事業に関する基本協定」を締結している。本協定の目的は、参画する2つの自治体と企業が資源やノウハウ等を共有し、持続性や環境への配慮、東日本大震災からの復興を念頭に、移動販売を実施、買い物環境に困っている町民を支援、地域の課題解決や行政サービスの向上、「未来につながる持続可能なまちづくり」を実現していくことだ。本協定取組みの一環として、イオン東北が事業主体となり、6/10(金)から2町において、特定復興再生拠点区域等、買い物支援の需要が高い地域を対象に、移動販売を実施する。2町は避難指示解除に向け、イオン浪江店を拠点とした買い物環境の充実・整備を行い、町民や新たに町に移住する人々が安心して暮らせる地域社会の実現を目指す。さらに2050年カーボンニュートラル社会に向け、当該事業で使用する車両は、トヨタ自動車とイオン東北が水素を燃料とした「世界初*」(*2022年4月現在 トヨタ調べ)となる燃料電池移動販売車を導入することとした。これ以前に、浪江町、双葉町、南相馬市、日産自動車㈱、フォーアールエナジー㈱、福島日産自動車㈱、日産プリンス福島販売㈱、イオン東北㈱、日本郵便㈱東北支社、㈱長大、㈱ゼンリンは、令和4年3月29日に、「福島県浜通り地域の3自治体と全国8企業、未来のまちづくりに向け共同声明を発表-先進技術とサービスで、持続可能なまちづくりの実現を目指す-」を発表しており、浜通り地域のまちづくりに向け共同声明を発表している。この発表では、浜通り地域において、わくわくする先進技術とサービスで、人とひとがつながり夢があふれる住み続けたいまちの実現を各自治体の復興状況やニーズに合わせて、段階的に目指していくとしている。こちらの内容は、1.実証が進むスマートモビリティのまちへの定着および自由な移動の実現を目指す。2.電気自動車およびそのバッテリーの蓄電池活用などを通じ、再生可能エネルギーの地産地消によるRE100*を目指す。3.地域コミュニティの中で、新しいヒト・モノと出会える機会を創り出し、にぎわいの創出による未来につながるまちづくりを目指す、というものだ。南相馬市が入るか否かに違いはあるが、「特定復興再生拠点区域等における水素燃料電池自動車を活用した移動販売事業に関する基本協定」と「福島県浜通り地域の3自治体と全国8企業、未来のまちづくりに向け共同声明」の三分の二は地域が重なる。「まちづくり」には、日産が、そのうちの一角を占める「移動販売」にはトヨタが参画する構図となった。2021年2月2日に日産が発表している「福島県の3自治体と全国の8企業、「福島県浜通り地域における新しいモビリティを活用したまちづくり連携協定」を締結」の概要においては、(1)新たな移動手段となるモビリティサービス、(2)再生可能エネルギーの利活用、低炭素化に向けた取り組み、(3)コミュニティ活性化、(4)強靭化が発表されており、うち(1)では過疎地や復興地域においても持続的、かつ、期間・交流人口の段階的な増加にも対応しうる公共交通サービスの構築を目指すとし、生活の利便性の向上、経済、産業の活性化へも貢献する、自由な移動や物流手段の実現を目指すこと、(2)では、電気自動車や定置型再生バッテリーを利用したエネルギーマネジメントシステムの構築と合わせ、各種施設や域内店舗での再生可能エネルギーの利活用を向上させ、低炭素化への取り組みを加速させるとしている。一方、「特定復興再生拠点区域等における水素燃料電池自動車を活用した移動販売事業に関する基本協定」における【本協定に基づく4者の主な役割】のトヨタの項目を見ると、同社は買い物支援策の実施にあたり、革新的で安全かつ高品質なモノづくりやサービスの提供を通じ、「地域社会の皆さまの幸せ」をサポートする、より良いモビリティ社会の実現を目指すとしながら、世界初の水素燃料電池移動販売車による、次世代を見据えた車両提供を実施します、としている。自動車メーカー2社が「フクシマ」において織りなす構図は、電気自動車(EV)vs水素燃料電池自動車(FCV)の「競演」でもある。周知の通り「フクシマ」(福島県浪江町)には、2020年3月7日にNEDO、東芝エネルギーシステムズ㈱、東北電力㈱、岩谷産業㈱が建設してきた、世界最大級の再エネを利用した世界最大級の水素製造施設「FH2R」(福島水素エネルギー研究フィールド)が完成、稼働を開始している。同施設は、製造・貯蔵段階では、風力、太陽光、地熱などから電力を得、水素を製造・貯蔵し、輸送段階では、水素を需要に応じて輸送する。供給・利活用段階では、FH2Rで製造された水素が、水素発電(燃料電池)で利用され、電力を市場に供給したり、水素ステーションで利用され、燃料電池車や燃料電池バスなど、モビリティ用途で利用されたり、産業用途においては工場などで利用されるとの仕組みだ。浪江町の吉田町長は、今年4月1日に掲載された同町ホームページの「【町長インタビュー】令和4年度の取り組みについて」で、今年度は特定復興再生拠点の準備宿泊が始まり、帰還困難区域の解除に向けての取り組みについての質問に対し「末森、室原、津島の特定復興再生拠点は、令和5年度春の解除に向け整備が進む。解除には町民が安全安心に生活できることが大前提だとし、津島地区には活性化センターに役場支所を置き職員も配置すること、また、拠点内には公営住宅や消防屯所を整備、少しでも買い物ができるよう移動販売車を計画している」とコメントしていた。また、多くの復興事業が行われている浪江町は、水素の利活用や駅周辺の再開発などを町の魅力として発信、「浪江町は面白い」と皆さんに思っていただくことで「帰りたい」「住んでみたい」「行ってみたい」につなげたいとしている。*ちなみに同町の駅周辺の整備事業には、隈研吾氏が参画している。双葉町の伊澤町長は、5月31日に双葉町産業交流センターで行われた「特定復興再生拠点区域等における広域移動販売事業実施に伴う基本協定締結式」において、「双葉町では現在、町内でスーパーやコンビニエンスストアが再開していないことから、避難指示解除を間近に控える双葉町にとって、この移動販売事業は町内の買い物環境整備に向けた第一歩として大変意味のある取組だと考えております」と挨拶を述べている。イオン㈱とイオンリテール㈱は、2016年11月17日に~「地域エコシステム」が生み出す新たな顧客体験~千葉市花見川区でのお買い物支援「移動販売車」の運行開始を発表しており、「移動販売」に一日の長がある。この際は、同社が進めていた「地域エコシステム」における「ヘルス&ウエルネス:身も心も豊かに暮らせるまちづくり」の一環として、増加する高齢者人口を見据え、特に高齢者の買い物を支援する目的で移動販売を行っている。また同時に千葉県千葉北警察署と結び、「移動販売車」の営業を通じ、高齢者の運転免許自主返納の情報提供や促進、「移動販売車」に搭載されているドライブレコーダーを活用した地域の犯罪捜査などへの情報提供、事件・事故、災害などに関する情報の相互共有、地震・台風などの自然災害時に、警察署の求めに応じた罹災者に対する支援などを念頭に置いた。イオン㈱はイオンサステナビリティとして「東北創生」にも取り組んでいた。東北創生には、柱として4つの方針が定められており、同社はこれを元に様々な活動に取り組んでいる。一つは事業を通じた地域産業の活性化、二つ目は雇用の創出と働きやすい環境づくり、三つ目は地域の未来を"ともにつくる"環境・社会貢献活動、四つ目は安全・安心にくらせるまちづくりである。同活動のニュースリリースの更新は、2018年2月26日「東北のさらなるにぎわい創出に向けて イオンは変わらず全国の皆様と東北の復興・創生に取組みます」で終了している。活動開始後、足掛け7年時点の情報だが、同社は地域産業の活性化を目指し、東北の優れた産品を販売するフェアとして、本州・四国の「イオン」「イオンスタイル」約300店舗で、東北6県の産品最大270品目を集めた「にぎわい東北フェア」を開催したり、東北地区の「マックスバリュ」において東北応援商品の特設コーナーを設け、産品の購入を通して、東北を応援したいという消費者の想いに応えた。また、2012年にイオン労使で立ち上げた「イオン 心をつなぐプロジェクト」では、2021年までの10年間に、延べ30万人の従業員によるボランティア活動、東北沿岸部での合計30万本の植樹を実施することを目標に掲げた植樹活動なども行っている。また2016年には「イオン 未来創造プログラム」では、持続可能なコミュニティの再生を目指し、地域住民や従業員の交流を通じた課題解決に取り組んでいる。ちなみに、同プログラムの当時の活動地は釜石市、大槌町、遠野市米通地区、気仙沼市大島、丸森町耕野地区、南三陸町、浪江町、二本松市、南相馬市小高区、鏡石町であった。日経新聞によると、2町に投入される「水素燃料電池自動車」はトヨタの「MIRAI」の約1.2倍の水素6.6キログラムを搭載、350キロメートル走行することが出来るという。前述の福島水素エネルギー研究フィールドなどが供給する水素を浪江町内に2ヶ所ある施設で充填するという。この「移動販売車」には、冷蔵、冷凍、温熱庫があり、150キログラムの商品を搭載できるという。福島民友新聞によれば、食料品、日用品など最大500品目を扱う。避難指示が解除された地域9ヶ所と帰還困難区域のうち、特定復興再生拠点区域にあるJR双葉駅前の計10ヶ所(双葉町:町産業交流センター前、JR双葉駅東口、浪江町:幾世橋住宅団地、請戸団地、棚塩、立野、川添、苅宿、上ノ原、高瀬)を巡回する予定だ。浪江町では来春以降、津島、室原、末森地区の3ヶ所に拡大する予定だ。「移動販売車」の稼働は週5日。営業時間は午前10時~午後4時となり、曜日別に決めたルートで1日最大4ヶ所を訪問する計画だ。現在は「様々な課題を抱えつつ」ではあるが、今後も水素ステーションやEV用の充電ステーションが、全国津々浦々に増設され続けていくのではないかと思われる。2町で行われる電気自動車、水素燃料電池自動車の「共演」と水素エネルギーが、まち復興の力として持続的に利用され、住民の方や帰還される方の日常生活を支えるあらたな事例となることを願いたい。
EV充電時間3分の1に、ダイヘンの急速充電器のスゴい性能 他
6月1日 連続4回となった「グリーントランスフォーメーション(GX)に向けて<概要>」について、本日は最終日となる。昨日は、2050年CNを実現するために必要な方策(GX政策パッケージ)の中の「カーボンプライシング」周りの話題を書かせていただいた。新たな市場創造のための実践を行う場となる「GXリーグ」の存在について少し触れてみたい。経済産業省が2022年4月1日に発表した「440社の「GXリーグ賛同企業」と共に、カーボンニュートラルに向けた社会変革と新たな市場創造の取組を進めます!」を見ると、本年の2月1日に同省が公表した「GX基本構想」に対し、440社の企業が賛同、全賛同企業のCO2排出量について、公表された温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)に基づく算定・報告・公表制度による平成30年の公表数値で試算すると、総計で約3億2千万トンとなり、これは日本全体の排出量の約28%(産業、業務、エネルギー転換部門の排出量の約38%)を占める。これらの賛同企業とともにGXリーグの本格稼働に向けた議論を進め、2023年度にGXリーグを本格稼働する予定という。賛同企業の業種は、電力、ガス、石油などのエネルギー企業、鉄鋼、金属、化学、紙パルプ等のCO2多排出産業、自動車、電機、産業機械、食料品といった製造業、情報通信、金融、小売、建設、運輸などの多様なサービス業となる。企業規模は、スタートアップ、中小企業、外国資本の企業にも賛同を得ているとする。議論は既に始まっており(2022年4月以降)、https://gx-league.go.jp/ を足場として、社会変革を見据え、GXへの挑戦を行う産官学が協働し始めているという。カーボンプライシングの中で(経団連としての)「脱炭素税」に関する考え方は、前提として多くの企業はCNの実現やCN行動計画の推進に向け、「すでに多大なコスト負担を伴う投資を行っている」状況があり、炭素税の新規導入や地球温暖化対策税の税率引き上げでは、着実な削減が担保されず、エネルギー価格が高い日本において合理的ではないとする。GX実現に必要な財源は「GXボンド*」等を活用、としている。*CNに向けたトランジション及びイノベーションに関する技術の開発・社会実装に使途を限定し、GX実現のため発行する国債のこと。経団連としては炭素税の新規導入や地球温暖化対策税の税率引き上げについては慎重な態度を示しており、CNについての議論を行う上で、エネルギー関係諸税などの既存税制やFIT(固定価格買い取り制度:エネルギーの買取価格を法律で定める方式の助成制度のこと、主に再生可能エネルギーの普及拡大と価格低減の目的で用いられる)、省エネ法といった他の関連施策と補完関係・相乗効果を有すること(整理や見直しも必要)や、日本のエネルギーコストが国際的に割高な水準にある中、課税による負担が産業の国際競争力を損なわないこと、CN実現に不可欠なイノベーションの担い手たる企業の活力を奪わない、などの視点を欠いてはならないとする。経団連は、CNに向けた諸政策の最終項に当たる「攻めの経済外交戦略」については、地球規模でのCNへの貢献と海外の旺盛なグリーン需要の取り込みによる成長実現に向けて、攻めの経済外交戦略として、①途上国・新興国の脱炭素化を後押しするとともに、国内企業のビジネス機会を創出し、②水素・アンモニアやレアアース等の確保のための資源外交、③炭素国境調整措置(CBAM)への対応などを展開すべきだとする。①では、政府主導のAETI(Asia Energy Transition Initiative)や、CEFIA(Cleaner Energy Future for ASEAN)を通じたアジア諸国のエネルギー・トランジション支援、政策、制度構築等の環境整備、ODA(政府開発援助:開発途上地域の開発を主たる目的とする政府および政府関係機関による国際協力活動のための公的資金のこと)等の公的資金によるインフラシステムの海外展開等を通じた「アジア・ゼロエミッション共同体」の具体化や、二国間クレジット制度(JCM)について、COP26(第26回気候変動枠組条約締約国会議のこと、2021年10月31日~11月13日に英国グラスゴーで開催、パリ協定で定められた「1.5℃努力目標」に向け、締約国に対し、今世紀半ばのカーボンニュートラルと、2030年に向けた気候変動対策が求めることが決まった)での、市場メカニズムのルール合意を契機に、対象国の戦略的拡大、プロジェクトの大規模化、制度運用面の改善、国際標準・基準作りへの積極参画を行うべきとし、②では、関係国と協調の下、国際サプライチェーンの構築の加速、トランジション期におけるLNG等の化石燃料の安定的確保。エネルギー安全保障、経済安全保障の観点を踏まえた調達先の多角化、関係国との協調・連携を求めている。③では、製品単位当たり炭素排出量の計測方法のルール策定、CBAMの対象となる当該製品に生じる炭素コストの検証、競争相手国の実質的な炭素コスト等の把握、サプライチェーン全体のカーボンフットプリント(商品やサービスの原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通して、排出される温室効果ガスの排出量をCO2に換算し、商品やサービスに表示する仕組みのこと)の「見える化」等や、関係国との連携・対話を求めている。4日間様々な話題について言及したが、経団連は「グリーントランスフォーメーション(GX)」実現に向けた投資により、2050年度に1,000兆円経済を実現、としている。資料の最後に付された2019年度とGX実現シナリオの比較表では、実質GDP(*2011年度基準)は537.5兆円→1,026.8兆円、19年度比では+91.0%、年平均成長率は+0.9%→+2.1%へ。一人当たり実質GDPは、426.0万円→1,007.4万円。CO2排出量(*吸収分を除く)は、12.1億トン→2.3億トン、13年度比では、▲14.0%→▲81.5%と試算されている。*GX実現シナリオの「主な前提条件」は、毎年10.6兆円*のCN関連の追加投資を行うことで、投資主導の経済成長を追求。エネルギーの脱炭素化に加え、産業・経済システムが大きく転換し、イノベーションが発言するものとし、同じく一人当たりのGDPの前提条件は、2019年度は総務省人口推計、2050年度は国立社会保障・人口研究所の将来人口(平成29年推計、出生率・死亡率中位仮定)より計算したものとされる。そうこうしている内にも、エネルギー環境はどんどん変化する。6月1日、札幌地方裁判所は「津波に対する安全性の基準を満たしていない」として、北海道電力の泊原子力発電所の3基ある原発全てを運転しないよう命じる判決を下した。この判決を受け北海道電力は、「泊発電所の安全性などについて最新の知見を踏まえながら科学的・技術的観点から説明を重ねてまいりました。判決は当社の主張をご理解いただけず、誠に遺憾であり、到底承服できないことから、速やかに控訴に係る手続きを行います」とのコメントを発表している。一方、島根県議会は5月26日に松山市にある中国電力島根原発2号機の再稼働を賛成多数で容認している。「電力の安定確保や地域経済への影響等」から必要性を主張する声が多数を占めた。丸山達也知事は6月2日に可否表明を出す予定となっている。5月18日に原子力規制委員会は、福島第一原子力発電所に溜まるトリチウムなどの放射性物質を含む処理水について、東京電力が政府の方針に従って策定した、処理水を海に流す計画を了承している。炉心溶融、水素爆発から始まり、処理水問題、核燃料リサイクル、津波対策、断層問題、臨界事故、原子炉再循環ポンプ内部の破損、主蒸気隔離弁を止めるピンが破損、結果、原子炉圧力上昇し、中性子束高の信号による自動停止、蒸気発生器の伝熱細管が破断、55トンの一次冷却水が漏えいし、非常用炉心冷却装置が作動、ご信号により原子炉給水量が減少、原子炉が自動停止、低レベル放射性物質をアスファルト固化する施設での火災発生および爆発、定期点検中に沸騰水型原子炉の弁操作の誤りで、炉内の圧力が上昇、3本の制御棒が抜け、想定外で無制御臨界などなど、事故の事例には事欠かない。「原子力利用の積極的推進」には、人為的なもの、人為的でないものを含め、これだけのリスクも伴う。グリーントランスフォーメーション推進の上で、避けて通れないのかも知れないが、経団連の「リプレース・新増設を含む原子力利用の積極的推進」や、政権が「安全最優先の原発再稼働」を謳う責任は重い。前述した、原子力発電所の長期運転による発電費用は、陸上風力が最も高く17.7円/kWhとなり、原子力(長期運転)が最も割安で5.1円/kWhと表わされている。昨今の状況を見れば、差分の12.6円/kWhは高値と映る。陸上風力、太陽光、洋上風力が国内のリスクを吸収し、処理水を海洋放出せずともよいグリーンな環境を構築し、周辺諸国への積極的配慮を表す「攻めの経済外交戦略」の下支えとなり得るなら、これらの選択肢も現実味を帯びるのではないだろうか。エネルギー供給側・需要側ともに「イノベーション」を加速する必要がある。岸田首相は、5月31日、経済財政運営の方針「骨太の方針」案と、中核となる成長戦略「新しい資本主義」を示した。人材育成や所得向上を図る「人への投資」に加え、「科学技術・イノベーション」、「スタートアップ」、「脱炭素・デジタル化」の4本柱に投資を重点化する方針を示したという。脱炭素では、再生可能エネルギーなどへの投資に使途を限定する新たな国債「GX(グリーン・トランスフォーメーション)経済移行債」が創設されるとの報せを聞いた。